【Golden Circle発売記念INTERVIEW前編】Vo.原田夏樹が思うevening cinemaの「現在地」とは
- 2022年3月16日
- 読了時間: 14分
更新日:2022年3月25日
evening cinemaにとって、『CONFESSION』以来4年ぶりのフルアルバム、そして現体制初のフルアルバムがついに完成! タイトルは『Golden Circle』。インドネシア人のイラストレーター・Ardhira Putraが描いたカラフルなジャケットが示す通り、様々な年代・ジャンルの音楽・文化的要素が遊び心満載に積み上げられた内容に仕上がっています。「明るい曲が少ない」といわれる時代に、evening cinemaなりの肯定感をお裾分けできるようなアルバムを完成させました。
オフィシャルインタビューでは、前編・後編にわけて、ボーカル&ソングライター・原田夏樹が『Golden Circle』を語る内容をお届けします。まずは前編。シティポップや渋谷系だけがルーツではない彼らが今作のアルバムで目指したサウンドについて、そして、前作のEP『AUTHETICS』以降の活躍における意識変化や自身が影響を受けたものなどを聞きました。聞き手は、2017年リリースの2ndミニアルバム『A TRUE ROMANCE』の頃からevening cinemaを追いかけてインタビューしている、音楽編集者・ライターの矢島由佳子です。
「外に出られない時期が1、2年あったし、内省的にはなりたくなかった。突き抜けた明るさがほしかったですね」
――『Golden Circle』、できあがりましたね。原田さんがevening cinemaを始めた頃からずっとやりたかったことや頭の中で描いていたことが、一番理想の状態で形になったアルバムなんじゃないかと感じました。
原田:よかった(笑)。
――アルバム全体を通してのテーマは何かあったんですか?
原田:今回はテーマありきではなかったですね。全曲配信することを念頭において、2、3か月くらいに一遍ずつ出していくようなスケジュールの中で、アルバムを作るという最終目標はありつつシングルを切っていくならどういう曲かな、という考え方で作っていきました。
――アルバムができあがって、「こういうイブシネが出てるな」「俺、こういうこと歌ってるな」とか、何か自分で思うことはありますか。
原田:コンセプト的には今までと地続きだなって自分でも思います。サウンド面においては、「やりたいようにやってみる」を素でできたかなと感じていますね。「正解かわかんないけど、一旦やってみるか」ということを、ある程度の水準でできるメンバーが揃ったこともあって。「これはできないからなしにしよう」みたいな作り方ではなかったですね。
――なるほど。バンドの関係性や、それぞれのスキルがレベルアップしていることがやっぱりデカいですか。
原田:そうですね、デカいと思いますね。ここ1、2年は、デモを作る段階で「ここでこの人にはしゃがせよう」「この曲はこのパートが目立つようにしよう」とか、そういう脳みそを使って作ることができるようになりました。
――サウンド面においては、具体的にどういったことをやりたいと意識していたんですか?
原田:とにかく派手にしたかったんですよ。ジャケットを見ていただいてもわかると思うんですけど、めっちゃ派手でカラフルな感じを出したくて。ほとんどの曲が音数がめちゃくちゃ多いんですよね。崩壊する寸前まで音を入れてて。それが正解かはわからないですけど、とにかくその方向で突き進んでみるということは一貫してたかもしれないですね。
――そうしようと思ったのはなぜ?
原田:最近、特に洋楽とかR&B系のアーティストって、音数が少なくて緻密に計算されたかっこいいものが多いなと思って。僕もそういうものをやってみたいなと思ったんですけど、このメンバーで出す初めてのフルアルバムということもありましたし、すごく派手でお祭り騒ぎみたいな作品にした方が性に合ってるというか、自分に嘘をつかないかなって。いわゆる「チル」みたいな音楽も憧れはあるんですけど、今僕がこのメンバーでやっていくと考えたときに、とにかく4人の技術を全部見せつける作品にしたいと思ってました。だからドラムの手数も多い曲が揃ってたり。ほとんどの人は歌を中心に音楽を聴くと思うんですけど、今回僕は「バンドのアンサンブルを聴かせたい」と思って。しかも人間だけではなくて、その裏に重ねている僕が編集したシンセとかテクスチャーも含めて、歌も楽しめるけど歌以外にも楽しみどころがある、ごちゃーっとしたものが作りたかったんです。
――今のトレンドに対する天邪鬼さというよりも、4人でevening cinemaというバンドをやれている喜びから、そういう方向性にいったということですよね。
原田:そうですね、後者ですね。もし今も『CONFESSION』を出したときの体制(原田のソロプロジェクト)だったら、もしかしたら音数を減らして大人しめに歌ってファルセットを多めに使った曲をたくさん書こうという方向にいってたかもしれないなと思っていて。なんというか、ちょっと少年に戻った感じのアルバムにしたかったですね。
――ソロプロジェクトの頃から、バンドへの憧れがあるってずっと言ってましたもんね。それをついに手に入れられたことがすばらしいです。
原田:ずっとこの方向でやるかどうかはまだ僕もわからないですけど、今の段階でやりたいことを突き詰めた結果ではあるのかなと思ってますね。
――「少年」に通ずるかもしれないことでいうと、歌に出てくる主人公の性格も、今までよりあっけらかんとしていたりおちゃらけていたりする感じが多いなという印象を受けました。
原田:そうですね。社会で起きていることをそのまま反映させようとかはあまり考えないで作ったんですけど、やっぱり外に出られない時期がこの1、2年あったし、行きたかったフェスがなくなることとかもあったし……そういうことは、知らず知らずのうちに反映されているような気がします。あんまり内省的になりたくないなっていうのはありました。突き抜けた明るさみたいなものがほしかったですね。
「もともと好きだったものと改めて向き合う1年間だった。再発見が多い1年を通してこのアルバムができました」
――いつも原田さんとは分母分子論の話をしますけど(大滝詠一が唱えた音楽論)、前作のEP『ASTHETICS』では「世界史分の日本史が分母にきてる」、つまり洋楽にインスパイアされた日本人がやろうとしてることを目指した、という話をされていましたが、今作はまたちょっと考え方が違いますか。
原田:そうですね。そんなに切り分けて考えて作ってないかもしれないです。インスパイアされた作品には洋楽もあれば邦楽もありますし、二元論で考えないようにしようと思って作ったかもしれないですね。
――より、昔の音楽をどんどん遡って掘っていったのかなという気もしたのですが。
原田:めっちゃあります、その通りですね。この1年間くらい、服部良一という作家にはまってしまって。名前は知っていたんですけど「東京ブギウギ」くらいしか知らなかったんですよ。掘っていって、文献とかを読んでいたら、戦前から同じような作り方をしてたんだなというか、洋楽をどうやって自国の文化の情緒と融合させて昇華させるかをやっていたということを知って、「あ、歌は歌だな」と思って。結局、音とか技術の差はあれど、やってることは基本的にずっと変わらないなというふうに思ったのは大きいかもしれないです。あと、そのタイミングで、King Gnuの常田(大希)さんのドキュメンタリーをテレビで見たんですよね。そこで、音楽作りはカルチャーのミックスと親和性があるみたいなことをおっしゃっていて、今トップランナーの人もそういう考え方で作ってるんだと思って、それに勝手に後押しされたのもあります。
――まさに常田さんの曲作りは異なるものを混ぜ合わせる手法ですよね。今までのイブシネは70〜90年代の要素が強かったけど、今回は洋楽でもたとえばビートルズより、それのさらに前にあった音楽とかから引っ張ってきているところがあって、それが楽曲に深みをもたらしているなと思いました。
原田:そうですね、そこは意識したかもしれないです。それこそ『CONFESSION』のときは90年代を意識して作っていたんですけど、今回はひとつの時代にとらわれるというよりはもっと広い視点で作ろうと思って、結果、ウエイトが60年代とかに大きくなった感じですかね。
――世間では2000年代リバイバルがきてるというのに(笑)。
原田:そうですね(笑)。それも特に天邪鬼だからというわけではないんですけど。好きなことをやった結果ですね(笑)。
――60年代を掘っていったのは何か理由があるんですか。
原田:90年代、特に渋谷系と言われるシーンが、やっぱり僕に呪いのようにつきまとっていて。彼らが参照元としたのが主に60年代なので、一旦僕もそこに潜ってみようと思って何曲か書いてみたのはありますね。
――evening cinemaという名前が広がっていけばいくほど、「渋谷系」や「シティポップ」というラベルがつきまとっていたじゃないですか。それに対して「そうだけど、それだけじゃないんだけど」みたいな葛藤もありました?
原田:最近は、それはあくまで周りが決めることであって、僕はそこまで思ってないけど周りがそう言うならば別に、という感じの割り切り方はできるようにはなってきたかなと思います。「このジャンルと言えばこのアーティスト」と言われてて、でもそのアーティストは「いやそんなことないよ」と言ってるケースって、結構あるじゃないですか。
――あるあるです。
原田:あるあるだよねと思って。
――このアルバムはイブシネのルーツがシティポップ、渋谷系だけではないということが改めて示せる一枚だとは思います。CDのブックレットの最後には「Dedication」という項目があって、いろんな固有名詞が並んでいますよね。いろんな年代の音楽家だけでなく、文学とか野球関係の人まで。
原田:これは、この制作期間を支えてくれた人たちという意味合いで書きました。音楽関係の人はこの制作期間によく聴いた人とか、あと具体的に収録曲のリファレンスになってる人が多いんですけど。
――これまで話してくれた人物以外で、特に影響を受けた人や強烈に印象に残ってるものってありますか。
原田:阪神タイガースですね。
――おお!?
原田:去年はやたら元気もらえましたね。久々に野球の試合を見るために、僕はDAZNまで契約しました。去年、上半期は1位で独走してたんですよ。「絶対優勝やろ」みたいな感じだったんですけど、失速して2位で終わって。ここ(Dedication)に入れるのはお門違いかもしれないけど(笑)、嘘はつけないので。失速したときも「なんでだよ、あとちょっと頑張れよ!」とか思っちゃうほど熱くなってる自分がいて、「これだけ熱くしてもらえたんだ」という意味で「ありがとうございます」と思ってここに入れました。
――この1年半、原田さんは外仕事もかなり増えましたよね。つんくさん作詞・原田さん作曲で曲を書き下ろしたり、Rainychさんとのコラボで山下達郎さんの「RIDE ON TIME」をカバーしたり、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2021』の企画で楽曲のプロデュースを担当したり。大滝詠一さんの『雨のウェンズデイ/カナリア諸島にて』を公式にカバーしてevening cinemaとしてリリースしたことも、ものすごい話だと思うんですけど。
原田:もともと好きだったものと改めて向き合う1年間だったかもしれないです。それこそ大滝さんの曲とかも、今まで何百回も聴いたはずなのに、いざカバーしようとすると「俺、全然知らなかったんだな」と思ったり。再発見が多い1年を通してこのアルバムができました。
「自分たちに対してシティポップ的な側面も多少なりともあるとは思ってるので、外国の方から見たevening cinemaという視点でジャケットを描いてもらうのは、すごく面白そうだなと思った」
――『Golden Circle』という名前をつけたのはなぜでしょうか?
原田:オーネット・コールマンというジャズミュージシャンのアルバムを、去年一時期はまって聴いてて。そのアルバムタイトルに「Golden Circle」というワードが入ってて、「この単語、いいな」みたいな感じでストックしておいたんですよ。あとで調べたら、ビジネス用語的な使われ方の方がむしろ今は認知度が高くて、「なぜから始めよう」みたいな意味もあるということを知って。このアルバムはなぜから始めて、自分がやりたいことを実現するために嘘をついてない作品だなと思ったので、そういう意味でも『Golden Circle』がしっくりくるかもと思ってつけました。
――アートワークもすばらしいですね。シンガポール在住、インドネシア人のイラストレーター・Ardhira Putraさんに依頼したのは、どういう経緯だったんですか?
原田:僕がYouTubeで見つけちゃって。Engelwoodというアメリカのアーティストがいて、そのMVを担当してアニメーションも作ってたんですよ。Engelwoodは、濱田金吾さんのトラックをサンプリングしたりしてて、自分の曲作りとわりと近いんですよね。それで「このイラストレーターさん、めっちゃ好きなんですけどどうにかコンタクト取れませんか」って、レーベルにお願いしました。
――実際につながれて作品が完成したのはすごいですね。制作に関しては、どういうコミュニケーションがあったんですか?
原田:ある程度「この方ならこうなるだろう」と自分の中で予想が立っていたので、お任せしても大きく外れたものにはならないなと思って、最初はお任せでという感じでしたね。曲の揃い方を見て「とにかくカラフルに盛り込んでほしい」ということだけ言いました。ぴったり相性が合ったなと、できあがってから思いましたね。
――すごく面白いですよね。海外の文化をどう自国の文化と掛け合わせるのかという音楽作りを日本人はずっとやってきて、原田さんはその文脈をしっかりと継いで今実践してる方で、でも、今作のジャケットにおいては日本の文化を輸出して、海外の人が見た日本の文化と自国の文化を混ぜ合わせて作品を作り上げているという。
原田:自分たちに対してシティポップ的な側面も多少なりともあるとは思ってるので、外国の方から見たevening cinemaという視点で描いてもらうのは、すごく面白そうだなと思って。それこそ最近だと、The Weekendが亜蘭知子さんの曲をサンプリングしていたりしますよね。大瀧さんが過去のインタビューで、分母分子論の「世界史」「日本史」「日本史分の日本史」が横並びになってる、みたいなことをおっしゃってて。つまり、どれが分母なのかという意識が脆弱なままどれも並列に使うようになってきていると。まさに、それの極みみたいなことが今起きているなと思います。
――今作はまた葛西敏彦さんがエンジニア兼共同プロデューサーとして入ってる楽曲が多いですよね。そこも作品への影響が大きいのかなと思ったのですが、いかがですか?
原田:ミュージシャン的な視点でエンジニアリングをしてくれるのでやりやすいですね。あと単純に、葛西さんとのレコーディングが終わるたびに僕のレベルが上がってる感じがするんですよ。他のエンジニアさんにもそれぞれのよさがありますけど、葛西さんにはプロデュースまで関わっていただいてるのもあって、あそこまで深いところまで来てくれるエンジニアさんは葛西さんしかいなくて。できあがる音に関してもすごく信頼してるんですけど、精神的な部分で確実に経験値が上がってることを実感します。
――技術や知識の面だけではなくて、精神面もなんですね。
原田:そうですね。終わったあとスタジオで一杯二杯くらい飲みながら語らう時間が、とてつもなく血肉になってる感じがするんですよね。技術面でも、歌録りのときの歌詞カードの作り方とか、ボーカルディレクションのやり方とか、エンジニアの初歩的なことまで教えていただいたりして。それらが、実際に僕が楽曲提供の場でディレクションするときにすごく役立ってるんですよ。惜しみなく盗ませてくれる人です。
――懐がデカい! 野宮真貴さんの「スウィート・ソウル・レヴュー (duet with Rainych, feat. evening cinema)」のレコーディング風景の映像も拝見しましたけど、あんなのアホほど緊張しますよね?(笑)
原田:します、本当に(笑)。僕はこれまでインタビューとかでピチカート・ファイヴを言及してるし、好きって言ってるし、そういうことがやりたいと思ってやってたら……本当に会えちゃった、みたいな。野宮さんのボーカルディレクションをするとき、めっちゃ怖かったですよ(笑)。だって「いやもう、言うことなんてないですよ」みたいな。でも野宮さんのスタッフさんたちは「いや、原田くんに言ってほしいんだよ」って言ってくれるし。
――そういう場でも、葛西さんが盗ませてくれたことが活きたんですね。
原田:はい、活きました。
――野宮さんとの制作で印象的だったことは?
原田:野宮さんが「最近、明るい曲が少ないのよ」みたいなことをおっしゃっていて。それを受けて、人生を全肯定するような明るい曲を作りたいという気持ちがブーストされた感じはありました。やっぱり僕が憧れてきた人は、僕が考えそうなことをずっと考えてやってこられたんだなって、そういうところで思いましたね。
――肯定することがすごく難しい時代な気もしますよね。むやみやたらに「大丈夫だよ」って言っても響かないくらい現実が混沌としてるから。それこそ詞も音も技量のある人しか、なかなかちゃんと肯定してあげられる曲を書けない時代なんじゃないかなと思います。
原田:確かにそうですね。自分が追い求めている明るさって、最終的には肯定につなげたいんですけど、やっぱりどこかで陰りがあるというか。笑い泣きの感情を表したいというのが一番あって、それはほとんどの曲に出せたかなって思いますね。「燦きながら」は特に意識しながら作ったかもしれないです。
<インタビュー後半では、アルバム収録曲を全曲解説!>
こちらからどうぞ👇
インタビュー・テキスト:矢島由佳子



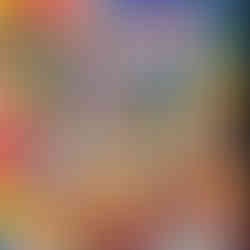




コメント